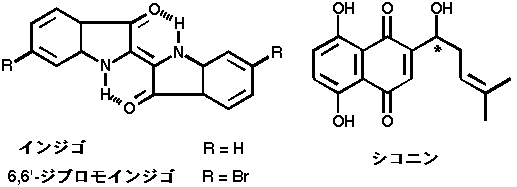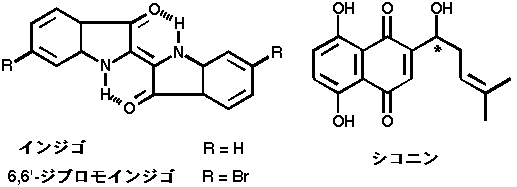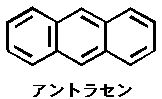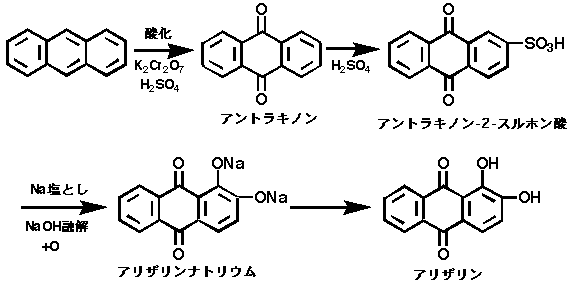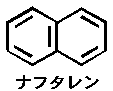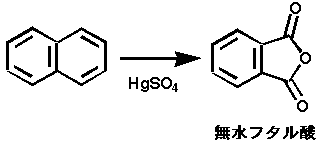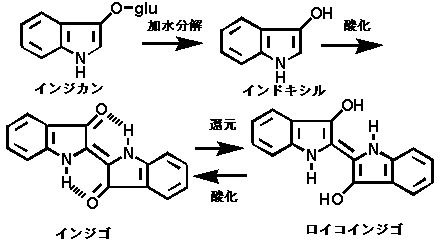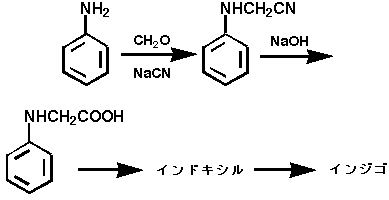からむこらむ
〜その67:人工染料の夜明け〜
まず最初に......
こんにちは。 ゴールデンウィークは皆様、どういう具合にお過ごしでしたか? まぁ、働いていた方もいらっしゃるでしょうし、ぼへ〜っと過ごされた方もいらっしゃったでしょうし..........
ま、これから色々と忙しくなりますね(^^;;
さて、今回は前回の続き、と言うことで。
前回は紫色にこだわってみましたが、今回は人工染料という部分で少しこだわってみようかと思います。 モーブの次に来たのは何なのか?
それでは「人工染料の夜明け」の始まり始まり...........
さて、取りあえずその66の続きと言うことで進めますか。
前回はパーキンが最初に人工合成した紫色の染料「モーブ」について触れましたが...............
「染料」と言っても色々とありますが..........ま、前回触れたのは
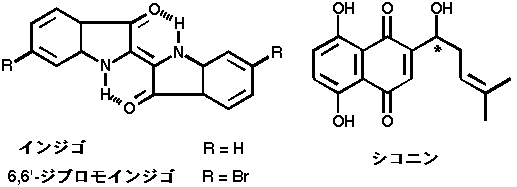
などを挙げてみました。 インジゴは藍色を。そして、構造の環(インドール環の)6の位置に臭素のついた、6,6'-ジブロモインジゴとシコニンは紫色を..........
さて、今回は人工合成の染料である二つの染料について触れてみたいと思います。 とは言っても、今回は「人工物」ではなく、自然のものを合成した、という話ですが............
実は、人工染料というもの。19世紀末には歴史を変えるまでの影響力を持つようになります。それまでの過程はどうなったのでしょうか?
取りあえず、最初に。時代の流れに沿って、赤色の染料について触れてみましょうか............
赤色の染料に「アリザリン」という染料があります。ま、理化学辞典なんて引いてみればその色を「美麗な紅色色素」と表記していますが........ このアリザリンは古代から知られており、エジプト人がミイラを包む布の染色にこれを使っていた、と言われています。つまり、それほど古くから知られている物、と言えます。
このアリザリンは世界中に分布しているアカネ科の植物の根から得られる、という事で結構世界的にポピュラーだった物なのかも知れません。 あ、日本でも昔からアカネ科から赤色の染料を取っています。
さて、時は1868年。当時ベルリンにはアドルフ・フォン・バイヤー(Johann Friedrich Willhelm Adolf Von Baeyer:バイエルとも)という、ブンゼンとケクレに学んだ高名な有機化学者がいました。ま、色々と業績を残している学者なのですが.......... 当時不明であった天然染料であるアリザリンの化学組成を彼は研究室でテーマとしました。 実はその数年前にはバイエルは別の天然染料であるインジゴ(上の物質。後述)の研究に乗りだしていたのですが...........彼はこのインジゴにおける研究の結果、ある方法.........複雑な有機化合物を亜鉛粉末と加熱して酸素を取り除くことで簡単/既知の化合物への変換方法...........を考案(化学構造の断片をつかむことで、組成を推測していくのに使う)。これをアリザリンに使用できると推測し彼の助手であったカール・グレーベ(Carl Grebe)とカール・リーバーマン(Carl Theodor Liebermann)にこれを用いての研究を指示しました。
さて、この二人。アリザリンの化学組成を知るために、指示通りこの方法を使用してみたのですが............出てきたのはコールタールの成分の一つであるアントラセンという化合物でした。
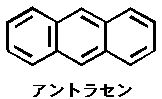
この頃には前回のパーキンの頃とは違って、すでにケクレによるベンゼン環の構造について提案済みでしたので、二人はすぐさまこの化合物の構造を特定することができました。
#ま、この事からケクレのベンゼン構造の発見がどれだけ偉大だったかが後になって良く分かるんですけど..........(^^;;
さて、とにもかくにもアリザリンを亜鉛粉末と一緒に加熱して出来たのがアントラセンである、ということがわかった二人。この後何をしたかというと..........この化学反応のプロセスの「逆」をたどることにしてみました。つまり、アントラセンからアリザリンを合成してみよう、ということになりました。
彼らがたてた逆合成の推測は........実は、現代の視点としては誤った考えだったのですが、結果的には面白いことに.............見事に、天然のアリザリンと同じ化合物を作る、つまりアリザリンの合成に成功してしまいました(^^;;
そしてこの瞬間は、人類が天然染料を実験室で合成した最初、となりました。
#前回やったモーブは、初の「人工染料」ですが、「初の天然染料の合成」ではありません。
この後、この合成法はどうなったか、というと........実は学術的には(当然のことながら)画期的な物であったのですが、アリザリンの工業的合成には適さないものでした。 では、どうしたかというと..........ドイツのバーディッシェ・アニリン・ウント・ソーダ工業会社(BASF)の技術者であるハインリッヒ・カロの助けを得てグレーベとリーベルマンは実用的と思われる合成法(つまり、工業的に安くて簡単な方法)を試験。結果、カロは高収量で標品のアリザリンに変えることの出来る構造不明の中間体を、(こちらも面白いことに)全く意図しなかった実験で発見してしまいました(^^;;
この合成法は面白いことに、モーブのパーキンがイギリスで独自に、偶然にもほぼ同じ時期に同じ発見をしたものだったそうです(^^;;
実は、パーキンは過去にアントラセンを扱っていた経験があり、グレーベとリーベルマンの報告を聞いて独自に研究。結果、1869年末にはパーキンの工場では1トンのアリザリンの合成を行い、1871年には年産220トンとなっていました。 つまり.......パーキンは前回の紫染料モーブに引き続いて、赤色染料アリザリンの工業合成にもたどり着いた(ただし、独自ではなく他者とほぼ同時)ことになります。
ま、ともかくもこの合成アリザリン。ドイツとイギリスの両国で1871年に市販を開始。 それまでの天然アリザリンの市場を駆逐してしまいました。
さて、現在ではこのアリザリンの合成法は広く知られており、結構色々な資料に掲載されています。
一応、下にその反応式を示します。
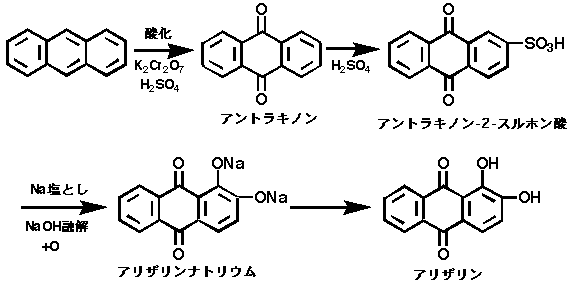
化学を知っている方は御存じの、フェノールの合成法にも関与する「アルカリ融解」という反応を用います。
さて、実はアリザリンだけでは木綿などを染められないのですが......... これをどう使うかというと........アルミニウム、鉄、スズなどの金属の水酸化物と結合して美しい色の不溶性沈殿(この金属塩を「レーキ」と呼びます)を生じ、この金属塩(媒染剤)を布につけて後染色して安定なレーキを生成。これによって堅牢に染め付くとされています。
尚、アルミニウム、スズで赤色。鉄で黒紫色。マンガンで褐色を呈するそうです。
さて、では次に........「藍色」を呈する、インジゴの合成までの話をしてみましょう。
青色染料であるインジゴは、アリザリンと同様に古代文明の時代から知られ、そして使われていました。日本でも前回挙げたように、徳島の藍染なんかが有名だったりします。
この染料。インド、中国から広まり、ヨーロッパに伝わったマメ科の植物「アイ」の葉から採っていました。古代の製法では、インドや日本において藍草の葉を水に浸し、発酵によって生じる黄色の液体を空気にさらすことによって酸化。これで青藍の沈殿が生成し、それを利用していたそうです。
上記の方法で生産された藍の染料は、19世紀末まで続き、1897年のインド(イギリス支配下)における藍の栽培面積は200万エーカー(約8000平方キロ)にも上ったとされています。 しかし............
さて、上記アリザリンにも出てきたバイヤーが、ベルリン大学でインジゴの化学構造の研究に着手したのはアリザリンよりも前の1865年のことでした。 結構長くかかったのですが、1883年までに彼はほぼ正しいと思われる構造を推定。よって、そのまま彼はその推定した構造の化合物の合成に着手しはじめました。 その結果、彼は天然の染料とあらゆる点で一致する化合物の合成に成功したのですが............. 残念ながらパーキンの発見したパーキン反応やら、その他様々な合成法を工夫してチャレンジしても、工業生産の点において。つまり、天然のインジゴと値段の点で勝てるという合成法が見つかりませんでした。
しかし、1893年。先ほどにも出てきたBASFにいたカール・ハイマンと言う人物がこの工業生産に初成功することになります。 彼はコールタールの一成分であり、当時の製鉄工業の廃棄物同然の扱いであったナフタレンという物質を出発物質に使ってこれに挑戦したのですが............
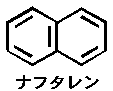
このナフタレン。鉄鉱石から鉄を取りだす際にコークスを使うのですが、このコークスを作るために石炭を加熱すると「粘性のある黒い、コールタール」が流出します。ナフタレンはこのコールタールに含まれていました。 もっとも、後年(そして今も)に合成染料や合成顔料の合成にこの当時「無駄」と思われたコールタールが大活躍するのがある意味皮肉なのですが..........(^^;;
さて、ハイマンがどうやって工業的合成法を見つけたのでしょうか?
この過程、面白いことにBASFのザッパーという化学者がナフタレンを発煙硫酸と加熱していたとき、たまたま温度計を壊してしまい、反応液中に温度計の水銀をばらまいてしまったことから始まります。 あ〜あ........と思ったのでしょうが.........しかしそれもつかの間。ザッパーは反応を見てみると通常の反応とは違う反応が起こることに気付きます。 それを調べてみると、それは.........ナフタレンが無水フタル酸、という化合物に変化したことが判明しました。 興味を引かれた彼らがこの経過を調べてみると、こぼれた水銀が硫酸と反応して硫酸水銀を生成。これがナフタレンを無水フタル酸へと酸化させる触媒となることが判明します。
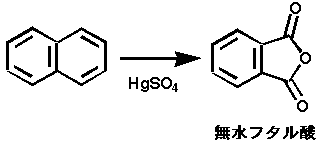
この無水フタル酸。実はインジゴへの合成は容易でして、BASFは早速着手。結果、1897年に合成インジゴを天然品より安い値段で販売を開始します。 その後もどんどん合成法が改良され、そして.......... イギリス支配下のインドを中心に盛んに生産されていた天然インジゴは経済的に大変動を来たし、結果。天然インジゴが染料市場においてかつての地位を取り戻すことはなくなりました。
まぁ、帝国主義全盛期の頃。 ドイツとしてはしてやったりだったのかも知れませんけどね..............
さて、では......取りあえず、自然界でのインジゴの合成経路を示しておきます(全合成経路は確認済み)。
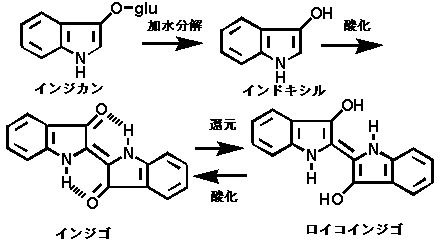
インジカンの「glu」ってのはグルコース、つまりブドウ糖のことです。 おそらくはアミノ酸であるトリプトファンから合成されるものと推測されます。
インドキシル二個が酸化してくっついて二量体であるインジゴが生成します。
しかし、工業合成ではこのような方法は用いておらず、アニリンから合成をしています。
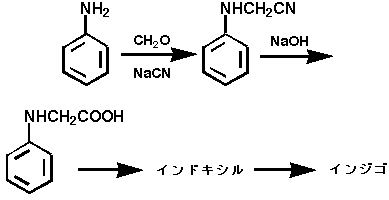
出発物質はアニリンです。 これを元に色々と反応させて水酸化ナトリウムでカルボン酸を生成。後に閉環反応でインドキシルを生成させ、ここからインジゴを作ります。
この方法は、「改良ホイマン法」と呼ばれています。
染色法ですが、少しひねっていまして...........
インジゴは暗青色で、ほとんどの有機溶媒に溶けにくい、という特徴があります。このままでは染められませんが、これを還元して生じる「白藍」であるロイコインジゴ(leucoindigo)はアルカリ溶液に可溶です。 よって、インジゴを一端ロイコインジゴにし、この溶液に布を浸して後、この布を空気にさらすと、ロイコインジゴは酸化反応を起こして、再び不溶性のインジゴに構造が戻ります。 こうして布を染色します。
このような方法によって染色が行われています。
さて、以上が合成染料の夜明け、なのですが.........面白いことに、前回話したモーブも今回の二つの染料も、色々な意味で「偶然」によって発見されるという奇妙な一致があります。 非常にこういう点が面白かったりします。
そしてこの後、コールタールから様々な合成染料が生まれます。 現在ではほとんどの染料が合成染料となっています。
これら合成染料は研究が進み、その染料としての構造研究はもちろんのこと、これらの一部のものはやがて、20世紀に入ってから様々な.......病原細胞などの「染色」の為に用いられ、そして面白いことにその中の一部には抗菌作用があることが判明するものが出来ます。 そしてやがて、いわゆる「サルファ剤」として役に立つものも出てくるのですが............
それはまた、別のお話。
長くなりました。今回は、以上と言うことにしましょう。
てなもんで、今回も「偶然からの発見」物語でしたが.........
さて、今回の「からこら」は如何だったでしょうか?
前回はパーキンとモーブの話でしたが、今回は人工染料の最初の頃についてと、その偶然の話を書いてみました。 面白いのは、合成染料の最初は偶然づくし、ということでしょうかね(^^;; もっとも、もちろんそれを観察して見抜いた彼らが優れていた、という意味でもあるのですが。
20世紀の前半はこういった染料が極めて盛んに研究されました。そして、染料のみならず生物学の方にも、ともかくも色々な方向に発展していきました。 しかし、その大本を見ると偶然から、ということが言えます。
非常に面白いものかと思います。
さて、次回は...........何にしましょう(^^; いくつかは考えているんですがね..............
ま、どうにかします(^^;;
さて、今回は以上です。
御感想、お待ちしていますm(__)m
それでは、次回をお楽しみに.............
(2000/05/09記述)
前回分 次回分
からむこらむトップへ