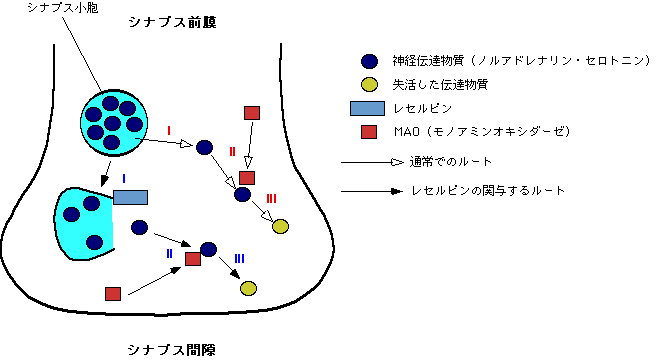
| ○管理人注: 2002年1月19日に日本精神神経学会は精神分裂病の名称を「統合失調症」に変更することを承認しました(8月に正式決定予定)。が、今シリーズでは統一性を持たせる為に名称の表記変更はしないこととします。 ご了承下さい。 |
| 作用(当時の推測) | 正常なラットへの投与後 | |
|---|---|---|
| イプロニアジド | MAO阻害 (もともと結核治療薬) | |
| レセルピン | 神経伝達物質の枯渇 (抗分裂病薬) | 抑制的 |
| イプロニアジド + レセルピン | --- | 活動過剰 |
| 分裂病患者 | 鬱病患者 | |
|---|---|---|
| イプロニアジド | 症状悪化 | 症状改善 |
| レセルピン | 症状改善 | 症状悪化 |
| イプロニアジド + レセルピン | 症状悪化 | -- |
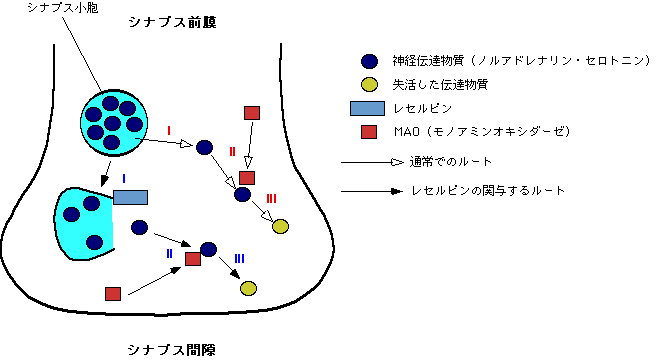
| 作用 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
レセルピン | シナプス前膜の小胞から伝達物質を漏出させる | → | 結果としてMAOによってノルアドレナリン、セロトニン、ドーパミンが枯渇 |
MAO | 小胞より漏れ出した伝達物質を失活させる | → | シナプス前膜での「安全弁」として働く |
MAO阻害薬 | 小胞より漏れ出した伝達物質を失活させず、 シナプス間隙で伝達物質の濃度上昇 | → | 神経伝達物質の濃度上昇し、伝達が強化される (鬱病改善) |
| レセルピン + MAO阻害薬 | 上記より ノルアドレナリンやセロトニン濃度が上昇 | → | MAO阻害薬単独より伝達がより強化される |
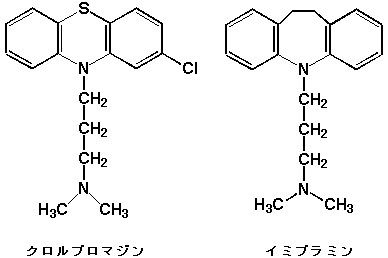
| 存在場所 | 働き | |
|---|---|---|
| AChE | シナプス間隙 | シナプス間隙及び後膜の受容体に結合した アセチルコリンの分解 |
| MAO | 神経細胞内部 | シナプス前膜で小胞より漏れ出した 伝達物質を失活させ、「安全弁」として働く |
(2002/02/19記述)