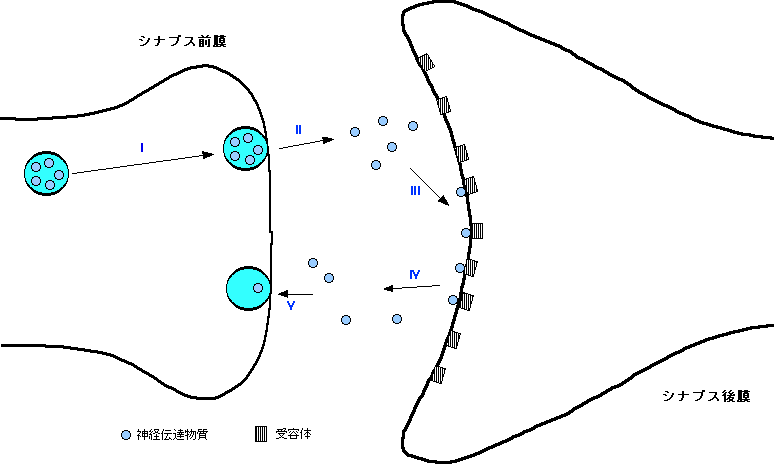
| ○管理人注: 2002年1月19日に日本精神神経学会は精神分裂病の名称を「統合失調症」に変更することを承認しました(8月に正式決定予定)。が、今シリーズでは統一性を持たせる為に名称の表記変更はしないこととします。 ご了承下さい。 |
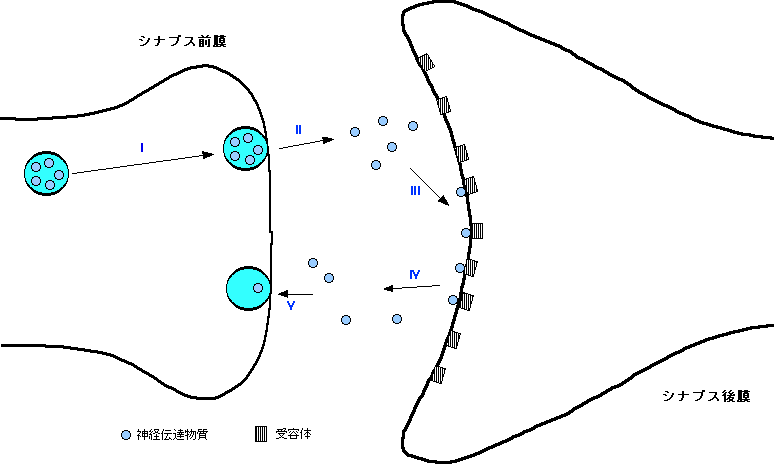
| アセチルコリン作動性神経 | アミン作動性神経 | |
|---|---|---|
| アセチルコリン | 神経伝達物質 | ノルアドレナリン、ドーパミン、セロトニンなど |
| アセチルコリンエステラーゼによる アセチルコリンの加水分解 (酢酸とコリンに) | 失活の機序 | 神経細胞にポンプ機構によって再び取り込まれる |
| 分解物は神経細胞に取り込まれて再合成 | 失活後の行動 | 神経細胞で再利用 |
| 作用機序 | 薬剤例 | |
|---|---|---|
MAO阻害薬 | MAOを阻害して、シナプス内の小胞より漏れ出した伝達物質を失活させない。 | イプロニアジド、フェネルジン、イソカルボキサジドなど |
三環系抗うつ薬 | アミン作動性の神経で、ノルアドレナリンの再取り込みを阻害する。 | イミプラミン、アミトリブチリン、ノルトリブチリンなど |
| 原因 | |
|---|---|
鬱病 | ノルアドレナリンまたはセロトニンが欠乏状態 |
躁病 | ノルアドレナリンまたはセロトニンが過剰状態 |
(2002/02/26記述)