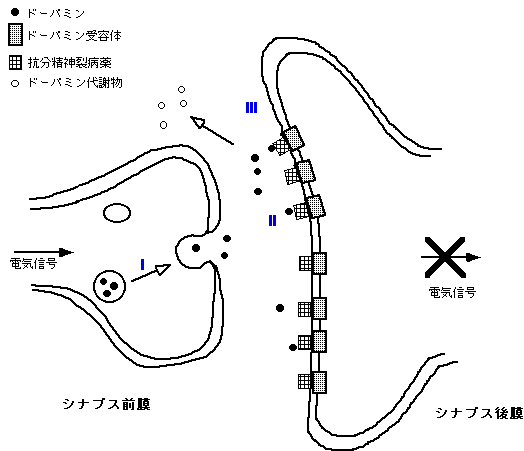
| ○管理人注: 2002年1月19日に日本精神神経学会は精神分裂病の名称を「統合失調症」に変更することを承認しました(8月に正式決定予定)。が、今シリーズでは統一性を持たせる為に名称の表記変更はしないこととします。 ご了承下さい。 |
| ドーパミン | ノルアドレナリン | セロトニン | |
|---|---|---|---|
| レセルピン | 減少 | 減少 | 減少 |
| クロルプロマジン | 正常値 | 正常値 | 正常値 |
| 濃度 | 代謝物 | 薬効との相関性 | |
|---|---|---|---|
| ドーパミン | 正常 | 上昇 | あり |
| ノルアドレナリン | 正常 | 上昇 | 無し |
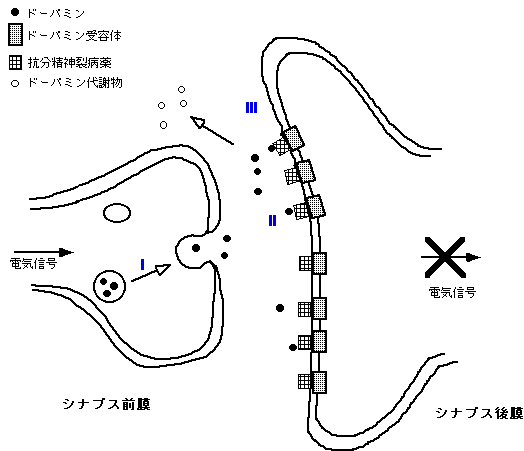
| ドーパミン量 | レセルピンによる発生/治療効果 | クロルプロマジンによる発生/治療効果 | |
|---|---|---|---|
| パーキンソン病 | 少ない | ドーパミンがシナプス間で枯渇することによる。 (他ノルアドレナリン、セロトニンも枯渇) | ドーパミンが受容体をブロック (アンタゴニスト)することによる。 |
| 精神分裂病 | 多い |
| 条件(ホモジネートと入れるもの) | cAMP濃度 | つまりは?(推測) |
|---|---|---|
| ドーパミン | 上昇 | ドーパミンは線条体にある受容体と結合 |
| 他の伝達物質 | -- | 物質と結合する受容体無し |
| ドーパミン+クロルプロマジン | -- | ドーパミンは受容体と結合できず (カールソンの仮説の支持) |
| ドーパミン+ハロペリドール | 上昇 | ドーパミンは受容体と結合 (カールソンの仮説の不支持) |
(2002/01/22記述)