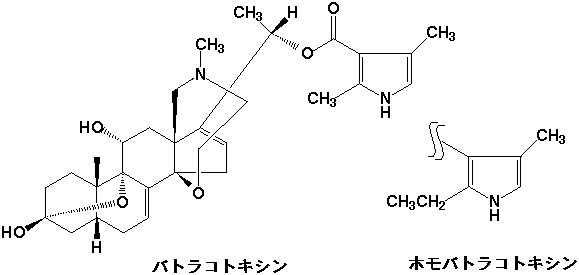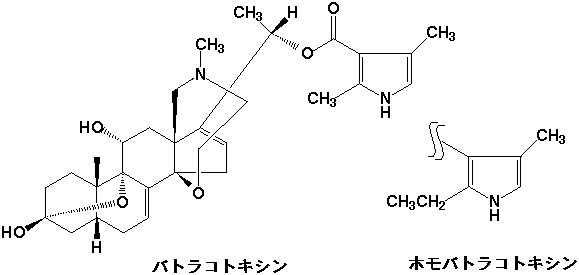からむこらむ
〜その210:ガマと毒ガエル〜
まず最初に......
こんにちは。今年もいよいよ後わずかとなりましたが、皆様如何お過ごしでしょうか?
ま、振り返れば非常に多くの出来事がありましたけど。色々と歴史に残る出来事が多かったように感じますがね.......ま、後世にどう評価されるのかは興味がありますが。
さて、今回のお話ですが。
前回は「鴆」と言う毒を持った鳥の伝説と、実在する毒鳥の話をしました。その中で出てきた物質にホモバトラコトキシンと言う物を挙げておきました。
今回はこの物質のさらに元となったバトラコトキシンとそれを作り出す生物について触れておこうかと思います。
それでは「ガマと毒ガエル」の始まり始まり.........
サテお立合
手前ここに取りいだしたるは筑波山名物ガマの油、ガマと申してもただのガマとガマが違う、これより北、北は筑波山のふもとは、おんばこと云う露草をくろうて育った四六のガマ、四六五六はどこで見分ける。
前足の指が四本、後足の指が六本合せて四六のガマ、山中深く分け入って捕いましたるこのガマを四面鏡ばりの箱に入れるときは、ガマはおのが姿の鏡に映るを見て驚き、ターラリターラリと油汗を流す、これをすきとり柳の小枝にて 三七 二十一日間、トローリトローリと煮つめましたるがこのガマの油。
このガマの油の効能は、ひびにあかぎれ、しもやけの妙薬、まだある大の男の七転八倒する虫歯の痛みもぴたりと止る、まだある出痔いぼ痔、はしり痔、はれもの一切、そればかりか刃物の切味を止める。
(ガマの油売りの口上より)
皆さんはガマの油売ってご存知ですかね?
筑波山、あるいは伊吹山名物の一つ、ですが........最近は知らない人の方が多いのでしょうか? 少なくとも「ガマ」などという表現は大分聞かなくなってきたようにも思いますので、知らないと言う人が多くても、と言う気もしますが。膏薬「ガマの油」を売り歩いた香具師(やし)でして、いつからいるかは不明ですが、江戸時代以降明治にかけて徐々に「売り口上」が有名となり、一つの芸にまで達した藻職業(と言って良いのか?)です。
「ガマの油」については口上を見ていただきたいですが。若干解説が必要なのは最後の方でしょうか? つまり最後の「刃物の切れ味〜」と言うのはガマの油を塗っておけば、刀で斬りつけられても切れないと言うものです。実際にはこの後に紙を用意し、刀で斬って「一枚が二枚、二枚が四枚」などと斬っていき、そして「ガマの油」を塗って切れなくなる、と言う物を見せるといった事をします。さらにはガマの油を塗った腕を、と言うのもありますが.......もっとも、管理人の家人によれば、家人が見た時に「ちょっと深く斬りすぎて.....」と言うちょっと洒落にならない(出血が止まらなかったらしい)事もあったようですが。
まぁ、それはご愛嬌(?)としておきましょう。
さて、このガマの油と言うもの。
文字通りガマガエル つまりヒキガエルをとってきて、その油をとるというものですが。一般に売られていたのが本当にそれなのかはよくわかりません(我馬の油=馬の油と言う説もあるようで)。しかし、実際にヒキガエルは身の危機に際して、耳腺や皮膚の分泌腺から白い油状物質を出すとされています。もっとも、よほどのことでない限りは出さないそうですが。
ところで、この物質は身を守るための毒液としてよく知られており、皮膚を触った手で目をこすると角膜炎になったりするようです。実際にやるとえらい事になるそうですが......「本当か?」と思われるかもしれませんが侮る事なかれ、犬や蛇、ネコ、イタチなどもこれによって撃退する様で、これをもって「不思議な能力」があるとされ、「がま仙人」などという言葉もできたと言われています。ただ、ガマの油による死亡事故と言うのは聞かない以上、「身を守る」以上の事はしないのでしょう。
この毒成分はよく研究されて知られており、一般に「ブフォトキシン(bufotoxin)」と総称される複数の毒成分で構成され、ブフォテニンやブフォタリン、ブファギン、ガマブフォゲンなどといった各種成分があります。代表としてはブフォテニンやブフォタリンでして、前者は基本的にはセロトニンなどに似た物質群でして、幻覚作用など。後者はステロイドの一種でして、強心作用などを持っています。
このガマの油、「毒」かというとそうではなく、実際に「蟾酥(せんそ)」と言う薬の材料に用いられており、漢方の重要な材料となっているようです。蟾酥は物の本をひも解くと「ガマを痛めつけてだす分泌液を集め、うどん粉とあわせてこね、これを陰干しにしたもの」とあります。これは内服でも外用でも使え、強心、沈痛、または解毒などに使われたとされます。実際、漢方などで検索するとよく出てくるでしょう。
もっとも大分高いようですがね。
#ちなみに、ヒキガエルの「ヒキ」は餌となる虫などが「自然に口中に引き込まれる」様に見えたことから、とされています。転じて「望みのものを引き寄せる」から縁起物となります。
ところで、上のような指摘がされるまで意外とピンと来ない人もいるようですが。
実はカエルと言う生物、「かわいらしい」から「気持ち悪い」まで色々と思う人はいるとは思いますが、これらの一部が「毒を持つ」という認識は余りないようです。もちろん、知っている人もいるとは思いますが、しかし一般的に「カエル」=「毒を持つ生物」と言う構図が容易に成り立つ、と言う人はいないでしょう。知っていてもガマのように「たいしたことはない」レベル。
ですが、自然は広いというべきか。この様式を容易に崩すカエルが存在しています。
ご覧の方の中でタイトルを覚えている方がいらっしゃるかはわかりませんが、過去に紹介した事もある本に石川元助の『毒矢の文化史』があります。
この本は、以前にも触れたように世界各地の毒矢の文化について触れたもので、それぞれの特徴から「文化圏」を設定し、そしてそれぞれに詳しく、その土地の人々の使い方や、歴史などについて触れた本です。
さて、この本で南米の矢毒として触れているのが「クラーレ」でした。具体的な内容は過去に譲ることとしますが、『毒矢の文化史』においては非常に詳細に、そして力を入れて紹介がされています。それだけ著名な存在であり、またよく知られ研究がされている。
ですが、南米における矢毒はクラーレだけなのか?
実際には異なりまして、中南米における矢毒とはクラーレとは限りませんでした。
1823〜24年にわたり、南米コロンビアを探検した人物として、コクランと言うイギリス海軍軍人がいます。
この人物、コロンビア探検において現地でのあるカエルの「利用法」を1825年に西欧社会に初めて(とされる)報告をしています。その利用法はなかなか印象的なもので、簡単に言えば「現地の人々はこのカエルを捕まえて、このカエルから毒を取り、それを矢に塗って毒矢として利用している」と言う報告でした。
このカエルは現地のインディアンたちに「ココイ(kokoi:「コーコイ」とする資料も)」と呼ばれるカエルで、背は黒色、二本の黄色の帯をもち、帯の間には黄色の斑点が存在しています。胴の長さは20mm程度で、体重は1g前後と小さい。水かきはなく、下草の葉の陰に隠れるようにいて、かわいらしい声で鳴く。現地ではこの鳴き声をまねて「返事」の鳴き声を聞き、そこから捕獲をし、木の葉で作った籠に入れます(著名な雑誌National Geographicに写真とともに記録されているようです)。
ま、人に言わせると「かわいらしい」カエルという事ですが......ココイについて、コクランはさらに記しています。
それによるとココイは竹筒のなかで飼育されます。ですが「毒を取る」ために飼われているわけで、やがて必要な時が来る。そしてその時が来ると.......毒を得るために「木の枝をのどに突っ込まれ、片方の脚まで通される」と猛烈なストレス(拷問でしょうが)を与えます。その時、ココイは特に背中に盛んに「汗」=分泌物を出し、それがやがて背中を覆う白い泡となります。これが強力な毒で、現地ではその白い泡に矢の先に塗る、あるいは浸すなどして陰干しにしてから利用します。
この効果は1年間は失われない、とあります。さらに白い泡の下には黄色い油が見え始め、これは4〜6ヶ月ほど効果を保つ致死性の物質で、これはかき集められて保管されました。
一匹のココイからは約50本分の毒矢を作るのに足る毒が得られ、そして「現地の人々によれば」それは「カエルの善意のたまもの」であるとされました。この毒はかなり強力な毒であることが知られ、わずかな量で簡単に獲物をしとめることができました。
このカエルに関する記録は他にもあり、この地を1934年と1955年の二回訪れたスウェーデンの文化人類学者バッセンもこのカエルの毒について記録を残し、「強い毒で、神経か筋に作用するようだ」と残しているようです。
さて、このような記録・報告があったもののココイの研究はなかなか行われていません。
最初のレポートとされるコクランの報告は1825年に行われたものの、それ以降に興味を持った人、少なくとも研究を行うほど肩入れした人は余りいないようです。
なぜか?
南米の、ココイのいる地域(コロンビア、パナマの一部、コスタリカ)はまずヨーロッパからすれば遠い地域であったことが挙げられるでしょう。そして、この地域はかなりの豪雨地帯で地域によってかなり違いは見られますが、森林地帯においては年間3000mmとも5000mmとも達すると言われており、この様な環境での調査はかなり困難な物があったと言えます。
それは実際に困難となっていたのですが........
さて、このようなココイですが。
そのココイその物もさることながら、科学者たちは当然その毒について興味を持つこととなります。そして、これはやがて一つのプロジェクトとして成立するようになりました。それは1960年代の初頭に米国から始まることとなります。
1961年、アメリカ国立衛生研究所(NIH)は動物収集家として著名なマルテ・レイサムにココイの収集を依頼されます。
レイサムはサンジュアン河において50匹を捕獲。そして、研究所に輸送されるのですが.......この計画、実はかなり難航を極めたようです。本来は研究所に輸送してから繁殖を試み、そして毒成分を調べると言う計画だったようですが、しかし実際には輸送中にことごとく死んでしまい、ココイの環境の変化に対する弱さがここで判明します。
結局、繁殖よりも毒成分の解明が急がれることとなり、結局は現地で捕獲してから皮膚をメタノール処理し、これを空輸して研究を行う、と言う方法がとられました。その数は1964年には5000匹ものココイが集められたと言われています。
さて、そのような中でココイには学名Phyllobates aurotaeniaが与えられ、そしてその毒にはギリシア語の「カエル」を意味する"batrachos"から「バトラコトキシン(batrachotoxin)」と命名がされます。そして数年の月日を経てその毒が得られ、そして正体も判明することとなります。
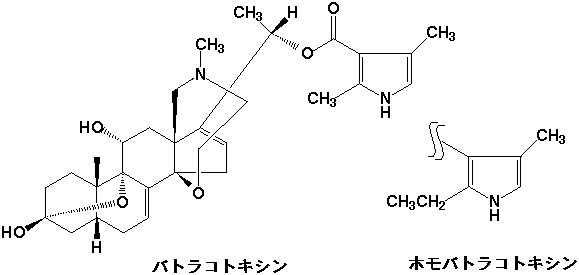
バトラコトキシンは1969年に構造が全て解明されました。
これは意外と時間がかかっています。専門的知識があれば構造(ステロイドに窒素の入ったアルカロイド)を見て、さらに当時の技術を考えるとそれも道理と思うのですが.......実は1964年の5000匹のココイの皮膚からはすでにバトラコトキシンとホモバトラコトキシン(当時はイソバトラコトキシンと呼ばれた)、さらにその類縁化合物が分離されています。その量、わずかにバトラコトキシンで11mg、イソバトラコトキシンが16mg、さらに弱い活性を持つバトラコトキシニンAが43mgとなっています。
これが5000匹の皮膚から得られた物です。たった50mgですらとれない、と言う世界なのですが.......そして、この頃には毒性もわかっていまして、LD50はマウスの皮下注射でバトラコトキシンが2μg/kg、ホモバトラコトキシンが3μg/kg、バトラコトキシニンAが1000μg/kgでした。
バトラコトキシンの毒性は特筆すべき高さでして、フグ毒テトロドトキシンの4倍に相当しました。ヒトでも体重60kgとして半数致死量がわずか120μg、ある程度「完全を期したい」(物騒な表現ですが)ならば200μg(1gの5000分の1)あればほぼ「必殺」に相当な毒性となります。
この高い毒性は当然のことながら研究者にとって障害になりました。
事実、現地でメタノール処理される皮膚からバトラコトキシンが出てくるわけで、それによってその作業に従事していたレイサムも意識不明(作業に使ったハサミで誤って怪我)に陥ったこともあり、また研究者たちも常にマヒ感などを味わったようです。「食べても胃で分解されるから」という意見もあったようですが、実際には軽いマヒ感は作業に伴っていたようです。
たとえ研究室の中であっても、研究者たちも命がけ、と言うことですかね......
こうして判明したバトラコトキシンはやがて機構も調べられることとなります。
これは見込まれていた通り神経系に作用することが知られていまして、他の(今まで挙げてきたような)神経毒に近いものがあります。具体的には神経細胞に作用し、そのナトリウムイオンチャンネルを開けっ放しにして脱分極を引き起こし、そのために神経の作用がかく乱されて死に至ると考えられています(その73参照)。
#ただし、ナトリウムイオンチャンネルはすでに開いてある必要があるらしいですが。
これは興味深いことにテトロドトキシンとは逆(TTXはナトリウムイオンチャンネルに「蓋」をしてかく乱)の作用でして、もしTTXがあるとバトラコトキシンの作用を阻害することが知られています。まぁ、だからといってココイとフグを一緒に食べれば平気、かどうかは別問題でしょうけど。
なお、ココイはなぜバトラコトキシンに耐性があるかというと、ココイのナトリウムイオンチャンネルは構造的にバトラコトキシンと作用しないようになっているから、となっています。ちゃんとそれ相応に、と言うことになりますが。
さて、このように知られた「新しい毒」であるバトラコトキシンは天然物化学の世界で有名になるのですが。
この毒が前回触れたように、「伝説」であった「毒をもった鳥」の存在に繋がってまた有名になります。それがニューギニアピトフーイでして、その部分は前回を読んでいただくこととしましょう。ピトフーイはバトラコトキシンの類縁化合物(メチル基かエチル基か程度の差ですが)であるホモバトラコトキシンを持つのですが、ココイは両方持っている以上やはり「カエルの毒を持つ鳥」と言えます。
このように全く関係がなさそうに見える生物が、しかも中南米と東南アジアという非常に離れた地域で見つかった事は学者たちの興奮を引き起こした事は言うまでもないでしょう。
そして、自然の不思議さでもあるのですが........
ところで、このような猛毒を持つココイですが。
他にも同じような存在はないのか? 実はその後の研究からココイのすむサンジュアン側より南にあるサイジャ河と言う太平洋側に注ぐ川があるのですが、ここで見つかった単色のカエルが毒ガエルとして知られています。学名をPhyllobates terribilisと言うテリビリスフキヤガエルと言うカエルがそれでして、体長40mm程度のこのカエルが非常に「凶悪な」カエルであることが知られています。
どういう点で「凶悪」か?
ココイはストレス(というか拷問というか)によって毒を出しましたが、このカエルは常に背中から分泌液を出しており、これにバトラコトキシンが含まれていることが知られています。現地に住むエムベラ族はこのカエルをやはり吹き矢に塗って「毒矢」として用いている事が知られているのですが......当然このようなことから「触れるだけで」危険という、学名に表されるようなまさに「恐ろしい(terribilis)」カエルといえます。
このカエルもやはり研究されるのですが、おたまじゃくしの頃は毒を作らず、やがて変態後に毒が生産されることが知られています。もっとも、成長したものを研究室で飼育すると毒は1年で半減し(ただし消えるわけではない)、二代目からは検出はされないそうですが。そして、自然の中でも直射日光や乾燥に弱いので実際には下草に隠れて住み、このような事情もあってか1匹からは2、3の矢じりを作る程度と言われています。
ちなみに、自然が奥深いと思うのはこのカエルにも天敵が2つある、と言うことでしょうか? それは一つはヒト。そしてもう一つはある種のヘビだそうですが.......まぁ、「絶対」はないということの好例なのかもしれませんけどね。
さて、長くなりましたが。
以上が前回触れた「毒鳥」の毒の「オリジナル」と言うべきカエル、ココイの毒の話となります。ただ、やはり不思議なのは「なぜカエルの毒を鳥が持つのか」と言う部分もあるのですが。ここら辺は自然の不思議、と言うことになるのかもしれませんがね。
ま、バトラコトキシンの他にも、色々と毒を持つカエルはいるのですが。そこら辺は別の機会に譲ることとしましょう。
それではこの話はこれで以上、と言う事で......
ふぅ...........
さて、今回の「からむこらむ」は如何だったでしょうか?
一応、前回の続き、と言うより「つながりがある話」と言う感じになりますけどね。まぁ、前回のリリースから少し時間を食いましたが、どうにかこうにか公開できたかと思います。
ま、当初はガマの話でそのまま突っ切ってしまいそうな勢いがあったんですけど(^^; さすがに、と言うことで。取りあえず本題に触れることができました。ま、とにかくもここまで凶悪な毒を持つカエル、と言うのも非常に興味深いものですが、同時に「なぜ遠く離れた島の鳥がこれと(ほぼ)同じ毒を持つのか」はよくわかっていません。
こういう部分にも色々と興味深いものはありそうですが.......真相はどうなのでしょうかね?
さて、そういうことで一つ終わりですが。次回はどうしますかね......と言うよりいつになるでしょうかね(^^;
ま、合間を見つけては書きためていこうかとは思いますが。さてさて.......取りあえず、どうにか、と思います(^^;
そう言うことで、今回は以上です。
御感想、お待ちしていますm(__)m
次回をお楽しみに.......
(2003/12/30公開)
前回分 次回分
からむこらむトップへ