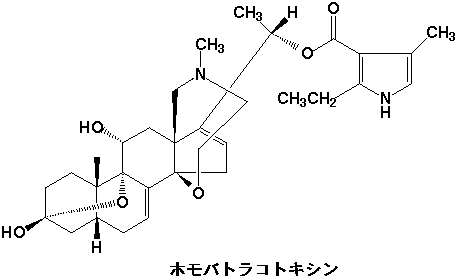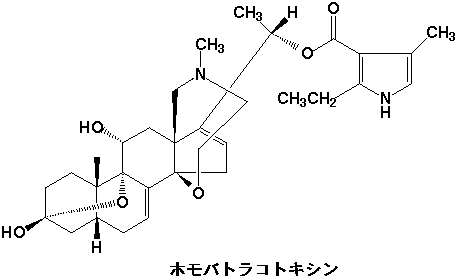からむこらむ
〜その209:鴆〜
まず最初に......
こんにちは。年末へ一直線となっている昨今、皆様如何お過ごしでしょうか?
いやぁ、何つぅか「師走」と言うことで、色々と周辺が走り回っていますけどねぇ........
さて、久しぶりの「からむこらむ」ですが。
え〜、まぁ本当に社会復帰して忙しかった訳ですけど。とりあえず、少し時間の合間を見て一つ作ろうかと思いまして........何かというと、伝説の毒、について触れようかと思います。とは言っても、完全に「伝説」と言うにはまた色々とある話なのですがね。そして、それがまた広がっていくこととなりますが......
それでは「鴆」の始まり始まり...........
皆さんは「有毒な物」と言うとどういう物を思い浮かべるでしょうか?
色々と思いつく物は多いと思いますし、そのいくつかはすでに過去の「からむこらむ」でも触れていると思いますが。たとえば青酸化合物は代表格になるでしょうか。あるいは鉛やタリウムも毒でしょう。ほかにもフィゾスチグミンやソラニン、クラーレと言う物もありましたし、大腸菌による食中毒やボツリヌス菌と言うのもありました。あとはテトロドトキシンと言う物もありましたか。
もちろん、ほかにも有害な物や有害にして有用な物をいくつも紹介してきています。まぁ、伊達に回数は重ねていないということでもありますけどね。
ところでこのような毒は実は分類が色々とできることに気付くでしょうか?
たとえば、鉛やタリウムなどは「金属」です。フィゾスチグミンやソラニンはそれぞれカラバル豆とじゃがいも、と言うことで植物由来。青酸化合物も植物に多いですか。クラーレも植物由来でした。さらに大腸菌やボツリヌス菌は微生物関係、そしてテトロドトキシンは動物由来という形になります。
それぞれに出自があり、そして特徴があるわけですが.......この中で動物毒に少し注目してみますと.........
たとえばテトロドトキシンはフグでした。ほかにも蛇やハチ、その他昆虫などとも毒を持つことはよく知られているでしょう。ですが、実際に「毒を持つ動物はどういうものがあるか?」と言われるとその範囲が意外と狭いことに気付くと思います。実際、毒を持つ動物と言うのはある程度固定化されてしまう傾向があるでしょう......ま、「毒を持つシマウマ」とか聞いたことはないと思います。それよりは、やはり昆虫の類いや一部魚類などを思いつくと思います。
話は変わって古代の話をしてみましょうか。
日本において本格的な法律の整備が行われたのは大体7世紀後半からです。もちろん7世紀前後のいわゆる「冠位十二階」や「十七条の憲法」といった聖徳太子の施政を思い浮かべる方もいらっしゃるかと思いますが、本格的な物は7世紀後半からと言えます。その日本の初期の法律は中国に倣って作られたのはよく知られている通りで、701年に出された(中学生の教科書にも出てくる)「大宝律令」がその最初となっています。
#これ以前にも律令はあるのですが、律令政治全盛に本格的・全国的に施行されたという点では最初といえます。
なお「律令」と言う言葉は「刑法」を意味する「律」と「行政・訴訟法」を意味する「令」より成っていまして、それをまとめて指す言葉となっています。
この大宝律令の原文およびその記録は現存はしていないのですが、その後手が加えられて757年に施行(制定は718年)された「養老律令」は基本的に大宝律令と同じと言われています。もっとも、これは字句の修正程度ではあるものの、付け加えられている部分もあることから「全く一緒」ではないのですが、しかしこの養老律令とその他様々な資料から、大宝律令の全容はほぼ正確に理解されていると言われています。
ところで、ひとまず中身がわかっている養老律令の「律」を成す「養老律」全13篇の7番目に、「賊盗律(ぞくとうりつ)」と言う錠分があります。これは殺人や反逆、強盗、窃盗といった重犯罪に対する規定でして、この中に当時における「毒薬」とその扱いに関する規定があります。
どういう規定か?
簡単に言えば「毒薬を人に使ったり売ったら絞首刑、売買しても使わなかったなら流刑」と言う物です。そして、ここで言う「毒薬」とは現在とは異なっていまして、「冶葛(やかつ:正確には葛は下が「ヒ」ではなく「人」のほう)」、「烏頭」「附子」「鴆(ちん)毒」と言う物が挙げられています。「冶葛」と言うのはゲルセミウムと言う、ビルマやインドでとれる植物の根から調製された生薬でして、中枢神経に作用しマヒを起こします。もっともこれは神経痛の治療にも用いられまして、正倉院や法隆寺に残る薬物帳にも記録されるなど「毒」の側面だけではありませんが......これは日本に(おそらく中国経由で)結構な量が輸入されていたようです。そして、烏頭や附子はトリカブトの母根と子根でして、これも毒として、あるいは薬として使われていました。細かいのは過去のものを参照していただきたいですが。
この三つはいずれも植物毒です。が、しかし最後の「鴆毒」と言う物。これはなかなか聞きなれない言葉だと思います。これは「鴆」と言う生物による毒なのですが、当時これは非常に恐れられた毒でした。
ところでこの中にある「鴆(ちん)」とは何か? 聞きなれない言葉だと思いますけど........
「鴆」と言う字を見ると「鳥」と言う文字が入っているのがわかると思いますが、実際にこれは「鴆」と言う「鳥」を意味しています。ならばこれはどういう鳥か、と言うとまた難しいのですが.......鴆の歴史そのものは古く、すでに紀元前の中国の様々な古書に記録が残されています。細かくやるときりがないですが、基本的には「クジャクに似て体は五色に輝き、背は高い」とされていまして、鶴のような足を持っています。そして黒い頚と赤い嘴を持っていまして、主として毒蛇(マムシなど)を好んで食べると言う鳥です。なおオスは雲日(うんじつ)、メスは陰訛(いんか)と呼ばれます。物によってはこれに「まじないで木を倒す」と言う様な話まで混ざっていますが。これについての代表的な記述は中国の薬学書として有名で、過去に何度か挙がっている『本草綱目』に絵とともに残されています。
ま、ほかにも様々な書物に記載がされていますので、きりがない物はありますが。
そしてこの鴆は食らった毒蛇の毒を体にためることができたためか、鴆の肉を食べれば必ず死に、その羽(鴆毛)も有毒。この羽を酒などに浸して(アルコール抽出ですか)、その酒「酖酒」を飲むとやはり死ぬとされました。つまり「毒をもった鳥」と言う非常に珍しい生物といえるでしょう。ただ、『本草綱目』においては、鴆の肉は生臭くて食べられず、しかも羽を酒に浸して飲んで死ぬなど事実無根であると指摘されています。
もっとも、鴆の肉や羽は市場に大きく流通 目的は言うまでもないのでしょうが していたという事ですので、その毒性は大きく信じられていたようです。そして、その特徴からか鴆の嘴はヘビよけとして、羽毛は蛇の毒消しとして珍重されたようです。一方、サイの角が鴆毒を消し去る力があったとされ、そのためにサイの乱獲が相次いだという話が残っています。
この鴆の毒、つまり鴆毒はかなり古来より、案の定と言うべきか暗殺用として用いられてきました。
古くはすでに紀元前7世紀の中国の古書『春秋左氏伝』に「酖酒」が出てきているとされ、その後『史記』といった史書も含めて様々な本に「鴆」や「酖酒」が登場しているようです。その記述は鴆そのものについてから、その毒についてが主眼となっている物など様々のようですが、毒殺に用いられる代名詞となったのは確かなようで、中国の文化を輸入した日本でもそれを恐れ、律の中の「賊盗律」による規制が行われたと言うことになるでしょう。
ですので、残されている話には中国の皇帝に生け捕りにした鴆を献上したところ、逆に皇帝の怒りを買ってむち打ちにされ、さらに鴆は焼かれたという話があるようです。当然、中国の律においても鴆は規制されまして、持っているだけですでに罪になると規定されていました。その内容は養老律の物と基本的に同じ、と言うよりそれをもとに養老律(あるいは大宝律)が作られたようですが。
さて、このような鴆と言う鳥ですが。皆さんは見聞きしたことがありますかね?
実はこの鳥、「想像上の」生物でして実在はしていません。様々な中国の古書に登場はしているのですが、中には紹介しつつも「存在は疑わしい」と書かれている物があったりと、昔から実在の疑わしさが指摘されています。
ま、所詮はその程度、と言うことなんでしょうけど。
しかし、鴆毒というか「鴆毒を名乗る物」は非常に多く流通していたと言われています。その毒性もある程度知られていたようで、症状としては肝機能障害による黄疸、消化器系を冒し、吐血や下血を引き起こすと言った物のようです。おそらく、「酖酒」を飲んだ人はこのような症状で死んでいったと思われますが.......
こう書くと「じゃぁ鴆毒ってあるんじゃないか」と言う事になりそうですが。しかし、実際に「鴆」と言う鳥は存在していません。でも、それを名乗る毒は存在する。
この矛盾はどういうことか? 実は、「鴆毒」と呼ばれる物の正体はその症状からヒ素なのではないかと考えられているようです。つまり、過去の一連のシリーズでやった中でも触れた亜ヒ酸といった物がこれに当たるのではないかと言われているようです。
過去にある程度ヒ素については触れていますが、中国でもヒ素はよく使われていました。
その内容はご他聞に漏れず毒としての使い方が多かったようで、紀元前からすでにヒ素を用いた暗殺の話には事欠かなかったようです。これは各国に見られる話とさほど変わりませんので、まぁ省略できるかと思いますが。その一方、薬という物についてもヒ素は使われることがありました。
例を挙げておくと、前漢の頃に成立した中国の古書『周礼(しゅらい)』には「五毒」として「雄黄(おおう:硫化ヒ素)」、「ヨ(「與」の下に石)石(よせき:硫砒鉄鉱)」、「石膽(せきたん:硫酸銅)」、「丹砂(たんしゃ:硫化水銀)」、「慈石(じせき:酸化鉄)」が挙げられています。ごらんの通り、5つのうちの2つまでがヒ素化合物となっていますが、『周礼』には「五毒」は医者がこれをうまく使って病気を治さねばならない、とされていました。
『周礼』は「五毒の薬」の作り方も紹介しています。その方法はまずこれらを素焼きの壺にいれ、その後三日三晩かけて焼きます。その後、白い煙が立ち上り、これを鶏の羽をかざして集め、器に掃きとるという物です。
さて、これをよく考えると?
五毒を熱すると、白い煙が立ち上る......この白い煙、何かといえば一つは慈石以外に含まれる、硫黄の酸化によって生じる二酸化硫黄と考えられています。さらに雄黄とヨ石のヒ素化合物からは......実は亜ヒ酸が得られることとなります。これ、実はその26で触れた土呂久ほか日本各地で行われた「亜砒焼き」と同じことが行われると言えます(「亜砒焼き」は硫砒鉄鉱を使った)。よって、この煙に鶏の羽をかざせば亜ヒ酸が付き、やがて温度が下がって固体となった亜ヒ酸の結晶が残ることとなります。
そしてこれを酒に浸せば?
当然、酒には亜ヒ酸が溶け込むこととなり.......毒酒となります。これを飲めば当然死に至る。そして、その内容などから先に紹介した「酖酒」はどうやらこれに当たるのではないか、と考えられているようです。つまり「鴆の羽」はこの猛毒の結晶をたたえた鶏の羽、と言うモデルがちゃんと存在していたと言うことになりますが。
先に書いたように亜ヒ酸は中国でも古来からよく用いられてきた暗殺道具でして色々と話が残っているのですが、「酖酒」もやはりこれに通じる物があったようです。
このような鴆とその毒ですが、しかし中国では徐々に鴆に関する記述は消えていったようです。
事実12世紀ごろを境に消えていったようで、明代や清代になると鴆に関する記述はあるものの、かなり「隅っこ」の扱いとなっているようです。特に実在に関しても特に興味がなかったようで結局は伝説ということになっていきます。事実鴆に関する話も曖昧で、鴆の肉を食べたと言う記録はあまりないとされ、取り扱いも酖酒などがメインとなっており、またそれも上のような話であれば........やはり実在は、と言う。
なお、日本ではどうだったのか?
養老律に見られた鴆毒は、その後『太平記』などに登場するものの、中国ほど相手にはされていないと言うのが実情のようです。もっとも戦国時代末期に「鴆毒」による暗殺が噂されたことがありました。
どういう話かというと、織田信長の後を継いだ豊臣秀吉は全国統一を成し遂げるのは皆さんご存知の通りかと思いますが.......秀吉は会津を武将として優れていた才能を持ち、勇名をはせた蒲生氏郷に与えています。この氏郷は実は色々とありまして......文禄4年(1595年)、氏郷は朝鮮出兵の最中、九州名護屋において突如発病します。さすがに病とあってか氏郷は会津に一度戻るのですが、しかしやがて会津を離れて京都に向かい、この地で死んでしまいます。死因は胃ガンだったようですが、このときの顔色が黄色であったために「鴆毒によって殺された」と言う噂がまことしやかに出回ったとか。
ちなみに、「犯人」は才能を恐れた秀吉とも石田三成とも言われていますけど......真相は不明です。そして、日本ではその様な話程度しか有名な物はないようです。
#ちなみに、その150の「良い毒の条件」で触れた話を併せると、なんとも言い様が無い物があります。
#毒殺が事実だった場合、「良い毒」とは?
以上のように「鴆」と言う鳥は伝説上の鳥だったわけですが。
自然界の中で「生物毒」と言う物を見ていった場合、実は鳥に毒を持つ物という物はまず知られていませんでした。事実「毒を持つ鳥はいない」と信じられていまして、「鴆」の否定以降は特にそう考えられたようです。
実際に我々の身の回りを見聞きしても、「毒鳥」なんてのは身の回りで見ることはないでしょう。カラスやスズメが毒を持つ、なんて話があれば色々と、それはそれで興味深いとは思いますがね。ですが、少なくともそんな物は知られていません。
では、「鴆」......いや「毒鳥」は存在しないのか?
じつに長い間、存在の可能性は示されながらも一般に(少なくとも欧米を中心とした世界では)「存在しない」と信じられてきました。実際にそういった事例を見ることがない.......ですが、これは現代になって覆されます。
1992年、国際的に著名な科学雑誌『Science』誌の10月30日号において、シカゴ大学のダンバッカー(ダンバッチャーとも? J.P. Dumbacker)らによって画期的な発表が行われます。これはそれまで知られなかった「毒を持つ」鳥の報告でして、さらに毒の正体を発表したものでした。
彼らの報告は極めて刺激的な物でした。
まず、彼らが報告したのは「毒を持つ鳥」が存在していると言うこと。これはそれまでの価値観を大きく覆すこととなりました。しかも、20世紀の後半に「やっと」見つかったわけですからこれは大きいことといえます。その鳥はニューギニアの密林に住む鳥で、オレンジと黒の鮮やかな色を持つ「ニューギニア・ピトフーイ」と言う、ピトフーイ(Pitohui:モリモズ)属の鳥でした。「ピトフーイ」とはこの鳥の鳴き声からとられた名前で、元々は19世紀ごろに命名がされています。
ピトフーイも色々と種類があるのですが、報告された毒を持つ鳥としては"hood pitohui(P. dichrous:ズグロモリモズ)"、"variable pitohui(P. kirhocephalus:カワリモリモズ)"、"rusty pitohui(P. ferrugineus:サビイロモリモズ)"と言う三種類の、手に乗るようなサイズの鳥でした。
これらの鳥、特にhood pitohuiは現地において"rubbish bird"、つまり「くず鳥」と呼ばれており、皮を取り去って特別に調理しない限りは食べられず、現地でも普通に食べることは無かったようです。さらには小鳥を捕食する生物もこのピトフーイはその毒ゆえか忌避しました。
この非常に画期的な発見がされた鳥は、論文が発表された『Science』誌の表紙を飾る事となります。
これらのピトフーイは、小さいながら羽と皮膚に毒を持っています。
その毒は非常に強いことが知られていまして、たとえば三種類の中で最強の毒を持つズグロモリモズは皮膚から10mg程度、あるいは羽毛から25mg程度をエタノールで抽出して、これをマウスに皮下注射させると20分以内にマヒを起こして死亡します。ズグロモリモズは胸の骨格筋にも弱いながらも毒があるとされていますが、しかし臓器には特にないようです。ほかの二種にも毒が認められていまして、ズグロモリモズほどではない物の、毒を持っています。ズグロモリモズに次いではカワリモリモズ、サビイロモリモズと続くようで、ズグロモリモズよりわずかに毒性が弱い程度となっています。どっちにしても強力ですが、カワリモリモズは皮膚と羽、サビイロモリモズは皮膚に毒があります。
ちなみに研究グループが毒に気付いたのは、興味深いことにこの鳥を捕獲した時に抵抗されてかまれたので、傷口をなめたら口の中がしびれたから、と言う経緯があります。さらに羽も舌にのせてみたら、くしゃみとともに口内の粘膜がマヒしたと言う..........まぁ、よく死なずにすんだ物ですが。
ところで、このようなピトフーイの話を検証すると、伝説の毒鳥「鴆」とのつながりがあるように見えてきます。
「鴆」と言う鳥その物は存在しない、と言うことは前にも触れた通りです。が、しかしそのベースとなった鳥がいる可能性は十分否定できないと言え、実際にそう考える人、つまり「ピトフーイが鴆の由来」であると考えている人がいます。もちろん格好などに関しては大きく違い(少なくとも足は長くなく、クジャクの様な鳥ではない)ますし、鴆の特徴である黒い頚と赤い嘴は一致しません。が、ピトフーイはオレンジと黒が特徴ですし、また古書に記載された「南方の国で」と言うのはニューギニアという土地から「中国の南方」である点で一致します。そして、「毒を持つ」のは確かですし、羽や肉、皮に毒がある。
もしかしたら、と言う可能性は十分にあるのかもしれません。
そして、もう一つピトフーイに関する情報を書いていません。何かというと毒についてでして......
先に書いたように、ピトフーイとその毒の論文が先の『Science』誌に報告されているのですが、ピトフーイの毒の正体もこの論文で発表されました。TLCやGC-MSといった機器により判明したその毒は「ホモバトラコトキシン(homobatrachotoxin)」と言うものでして、ズグロモリモズの体重65g中、皮一羽分に15〜20μgが、羽に2〜3μg分が含まれていました。この毒のLD50はマウスの皮下注射で3μg/kgと非常に強力なものとなっています。
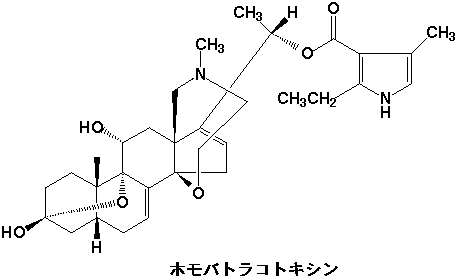
専門的ですが構造をみればわかる通り、ステロイド骨格を持っている物質です。
では、これの何が大きな発見なのか?
実はこの毒の類縁化合物にバトラコトキシン(batrachotoxin)と言う毒があるのですが(専門注:構造的には構造の右側のエチル基がメチル基)、バトラコトキシン自体は実は以前から知られている物質でした。それは南米に住む「ココイ(kokoi)」または「コーコイ」と呼ばれるカエルから得られる毒として有名で、これもまた発見当時色々と注目されたのですが.......
そのカエルの毒とほとんど同じ物が鳥にある。
この報告は非常に大きな物となっています。
では、ピトフーイの持つホモバトラコトキシンと言う毒がどこから来るのか、と言うのは未だ不明です。ただ、手がかりとなる物はあるようです。
興味深いことに報告された地域以外のピトフーイでは、たとえニューギニアであっても毒を持っていない様で、これは非常に興味深いものとなっていますが理由は現在不明です。少なくとも、ピトフーイ自身に毒を作り出す器官がある様には見えないことや、成鳥より幼鳥の毒性が弱い事などから、おそらくはフグの毒化と同じように、この地域のピトフーイの餌となる生物が毒を持ち、それを体内で保持するのではないかと考えられているようですが。
ただ、まだ「不明」と言うのが現状のようです。
さて、以上が鴆と言う伝説の鳥と、ピトフーイという現在知られる唯一の「毒を持つ」鳥の話となりますが。
伝説上の話と信じられていた物が覆る、と言うのはなかなか興味深い物であると思われます。が、さらにこれがカエルの毒とほとんど同じ物である、と言うのもまた面白い話であるといえるでしょう。
そうなると今度はこういう話も可能となります。
つまり、「そのカエルの毒はどういう物なのか?」。これがまた色々とあるのですが.......残念ながらスペースは無いようですので、次回の話としましょう。
そういうわけで、ひとまずこの話は以上、と言う事にしましょう.........
やれやれ.......
さて、今回の「からむこらむ」は如何だったでしょうか?
ま、あれこれ忙しかったんで少しずつ書きためていたんですがね。まぁ、どうにかこうにかできたようですけど(^^; ま、久しぶりなんでまたあれこれあるとは思いますが.......とりあえず、伝説の話から実在の話をしてみましたけどね。なかなか「鳥の毒」なんてのは思いつかないと思いますので、これはこれで興味深かったかと思います。
ま、実際にこれはかなり大きな話題になったんですけどね。だからこそ、『Science』誌で表紙を飾るなどしたわけですが。それがまだ約10年位前の話ですから、色々と自然は広いと言えるかもしれません。
さて、そういうことで一つ終わりですが。次回はこの話の続きといこうかとおもいますが。
まぁ、やっぱりいつになるかわかりませんので(^^; その点はご容赦を、と思います。
そう言うことで、今回は以上です。
御感想、お待ちしていますm(__)m
次回をお楽しみに.......
(2003/12/01公開 同12/02修正)
前回分 次回分
からむこらむトップへ