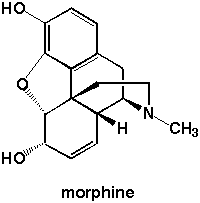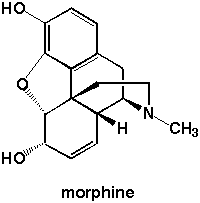からむこらむ
〜その117:夢の神と兵隊病〜
まず最初に......
こんにちは。ゴールデンウィークもついに終わりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
沖縄はついに梅雨入りしたそうですね。本州も徐々に夏の足音が近づいてきているのでしょうか?
さて、前回は「アヘン」の医薬を中心とした歴史の話をしましたが、今回からはその「中身」について触れていこうかと思います。
ま、色々と追及していけば「アヘン」というものが奥深いものですので、ある程度省かせてもらいますが.......ただ、アヘンの絡みは「史上初」がかなり絡んできたりしますので量は多くなってしまいますがね。ただ、そのいくつかは興味あるものになるかと思いますが.........
それでは「夢の神と兵隊病」の始まり始まり...........
さて、前回は「アヘン」の歴史についての話をしましたので、今回からはもっと深い話をしてみましょうか。
では、まず最初に「アヘン」とは何か、について触れておきましょうか。
これは前回にも軽く触れましたし、一般に良く知られていると思いますが、ケシという植物より得られる乳汁を固めたもの、簡単に言えば「抽出物」を指します。この抽出物はどうやって得るかと言いますと、ケシの花弁が落ちた2〜3日後に緑がかった「莢」が発達します。この莢は「ケシ坊主」という物でして、タイミングを見計らってこれにナイフで傷を入れ(このときにいくつかの注意がある)、そして出てくる乳汁を回収する、という方法で得られています。この方法は古くは(前回にも触れた)ディオスコリデスが記録を残していまして、現代でもこれは変わることはありません。
もっとも、最近ではこんな「面倒」なことはせず、ケシ坊主を回収して機械で潰して得るのが主流だそうですが........
こうして得たアヘンは実際には更にいくつかの工程を経て精製されていきます。
さて、このアヘンを生む「ケシ」ですが、この植物はどういうものか?
ケシはケシ科植物でして、真正のケシは学名を「Papaver somniferum」パパベル・ソムニフェルムと言います。これは1753年に植物学の大家リンネによって命名されました。英語では「poppy」がケシを意味しています。
さて、実際にはケシはじつに様々な種が存在していることが知られています。良く言われている通りアヘンを生みだすようなタイプのケシは極一部でして、上記ソムニフェルム種とセティゲルム種のケシぐらいしかアヘンを生み出すことが出来ません。このため、この二種は各国で規制の対象となっています。その他のケシはアヘンを生み出す可能性がない(または「極めて少ない」)ので植えてよく、ヒナゲシやオニゲシなど、我々がよく見かける物は規制対象外となっています。規制対象となるものとならないものには外見で差がありまして、分かりやすいものとしては全体的に規制対象となるものの方が大きく、茎は太くて丈夫です.......とは言っても、街中で見ることは「無いはず」ですがね。
#あったら大変です。
尚、丁度今の時期(5月)が日本ではケシの花が見られる季節となります。
ケシの原産地は欧州東部と言われています。今では各種のケシが世界各地にあり、日本でも街中で(規制対象以外の)ケシをよく見かけます。しかし、真正のケシはこの原産地ではそれほど大量には取れないようで実際には中東、西・中央・東南アジア地域で大量にとれやすいようです。また、土壌条件などが結構厳しいようでして、場所によっては育ちにくく、また連続した栽培が出来たり出来なかったりします。一般に寒いのを好むために高地の方が栽培に向くようです。栽培の場所・時期で出来るアヘンの質や量が異ることが知られています。ま、栽培に関してこれ以上詳しいことはやめておきましょう。
日本では漢字で「芥子」または「罌粟」と書き、一般に室町時代に入ってきたと考えられています。が、一説によると奈良時代に西アジアからの渡来人とおぼしき人名が残されており(シルクロードを通ってきた)、彼らが当時すでに持ち込んでいたのではないか(西アジアはケシの産地である)と考える人もいるようです。また、この前後に盛んだった仏教(密教)にケシが用いられていた(焼香や護摩など)可能性もあると言われています。江戸時代には津軽で栽培が盛んだったようです。
#ここら辺の名称との関わりを追及すると面白いのですが、長いので省略します。
アヘンを生み出すタイプのケシは通常は各国で規制が行われており、世界でも安定した国家の中では特定の国で生産されているにすぎません。その目的は大体は医療・研究用となっています。日本はこのケシを栽培していまして、厳しい管理体制の元に栽培が行われています(東京の施設でも作っていたりしますが)。ただし、一部の国家ではこの規制が緩いか行われておらず、西アジアや東南アジアの国々で非合法な栽培が大規模に行われています。特に東南アジアはミャンマー・タイ・ラオスを結ぶ「黄金の三角地帯」が有名だったりします(これが犯罪ルートに繋がる)。また、一部の情報ではアフガニスタンを現在実質的に支配するタリバーンがこのケシを使ったアヘン製造を積極的に行っているという話もあります.......当然、「聖戦の名を借りた人殺しの資金源」ですが。
余談ですが、日本では昔「アツミゲシ」という、北アフリカから渥美半島に帰化したケシがあり、これがアヘンを生み出す(セティゲルム種だった)と言うことが分かって愛知県警から自衛隊まで総動員して根絶した、という話があります(相当に大騒ぎだったようです)。
尚、ケシから取れるものはアヘン以外にも色々とありまして、その種は油を取ったりするのに使用もしました。また、パンなどに混ぜて食べていた様です。日本では、コンペイトウを作るときの「種(「核」という意味で)」として、または和菓子の飾りなどにケシの種を用いることがあるようです(もちろん、アヘンを作り出すタイプを使っているとは思えませんが)。
さて、ケシから得たアヘンの名称や薬効についても触れておきましょうか。
アヘンは漢字で「阿片」または「鴉片」と書きます。16世紀の中国で完成した『本草綱目』には「阿芙蓉」(あふよう)となっていたことから日本でもこの名称が使われることもあったようで、時代劇なんかでも時々この呼称を見ることがあります。この「阿芙蓉」の語源はケシが芙蓉に似ているから、という説とアヘンをアラビア語で「アフィウーン(アフュヨン)」と呼んだからという説があります。アヘン自体はこの後者の影響で名付けられたと考えられているので、後者の説が一般には説明に使われるようです。
アヘンの効果については前回話したものと重複しますが再度説明をしておきますと........
アヘンの作用の主力は「鎮痛作用」でして、ある特定のタイプの痛み(全てのタイプの痛みではない)を止めます。また、これと同時に不安や不快感、緊張感を消して安らぎをもたらし、睡眠をもたらします(この眠りはかなり「深い」ものとされています)。また、同時に多幸感や陶酔感を味わい強力な快楽感を味わうとされています。また、前回書いたようにアヘンが赤痢の薬であったように、下痢を止める作用もあります。これらの作用はいずれもアヘンが人間の中枢神経へ作用することを示しています(いずれもその110で示した物になります)。
アヘンの催眠に関する余談ですが、「オズの魔法使」の映画の方(戦前の映画ですが)を見ると、都に着く直前に西だったか東だったかの「悪い魔法使い」がドロシー達の道中を妨害するためにケシ畑を作りまして、ここを通ろうとしたドロシー達はこの中を歩いている最中に眠ってしまう、というシーンがあります。これは上記のアヘンが眠気を催すということを知っていると納得できるシーンだったりします(どうやって切り抜けたかは、実際にご覧になると良いでしょう)。
さて、アヘンのこう言った効果、特に多幸感や陶酔感による快楽は前回にも示したように「災い」をもたらすようになります。それは、この「快感」を得たいがために繰り返し使用する様になる、という事例でして、いわゆる「薬物乱用」に走ることが問題でした。これはアヘンが「麻薬」たる理由となります。これに中毒するとやめられなくなりまして、しかも最初は少量で効いていたアヘンも同量では効かなくなり、徐々に使用量を増加させていく様になります。そして中毒者がアヘンの連用をやめると苦痛、不安、鬱状態に見舞われることとなり非常に苦しむこととなります。また、悪寒、痙攣、発汗、のどの渇きを感じ、更に涙や鼻水が止まらなくなり、そして食欲が無くなり下痢症状に見舞われることとなります。これらは相当に苦痛を伴いますがアヘンを摂取すれば収まることから、またアヘンを欲しがる、という悪循環が出来ます。
こう言った乱用については完全にその111で話した物と一致します。量が増加していくのは「耐性」が発達するためでして、実際に中毒者は相当量(あるときは致死量以上)を使わないと「効かない」状態になります。また、中毒に陥ってアヘンを中断したときに出る症状は「禁断症状」でして、これはその111で話した通り「身体がバランスを保つため」にアヘンの働きを打ち消すべく「逆の反応」を行っていたのに、急にアヘンが無くなったのでこの「逆反応」だけが身体に出てきて苦しむこととなります。実際、最初のアヘンの作用とは正反対の症状が出てきます。この症状はアヘンを再度投与するか、数日間耐える他無く、前者ならば悪循環へ。後者に耐えられば「足を洗う」第一歩となります。が、相当に苦しむために中毒者は大抵は前者を選ぶ、となるようです。これは依存性の問題も関与しますが。
依存性については、アヘンは精神依存も身体依存も相当に強いことが知られています。しかも耐性が容易につきますし、禁断症状の苦しさもかなりのものですので、麻薬商人達にとっては「極めてありがたい」物だったようです。
もっとも、最近はアヘンなんかは使いませんし、時流としては「ハイ」になるものが好まれますのでこういうタイプのものは売れないそうですが。
ところで、アヘンの歴史については前回ある程度話しましたが.......近世に入って化学が発達しだすと、当然「アヘンの有効成分はなんなのか?」という疑問が学者達の間で出るようになってきます。この疑問に答えを出したのが19世紀初頭のドイツの薬剤師フリードリッヒ・ウィルヘルム・アダム・ゼルチュナーでした。
この活性成分の分離については色々とあるのですが、薬剤師ゼルチュナーが薬局での仕事の余暇にアヘンの研究を行っていまして、最終的に1803(1805とする説も)年に当時20歳(22歳)若さでアヘンの活性成分の分離と結晶化に成功します。しかし、通常はこの説が一般的に言われていますが、物の本や地域によっては「フランスのデローネが先だ」、という説もあります。実際、本などを見ていると著者や国でバラバラになっていたりします。
さて、これらの騒動はともかく、ゼルチュナーは彼が分離した成分が動物で実際にアヘンと同じ効果を持つことを確認し、1806年に薬学雑誌にこれを発表。そして、その後には元素分析などを行ってこれが炭素、酸素、水素、窒素を含むことを確認します。彼はこの物質に、アヘンが睡眠をもたらすことからギリシア神話の「夢の神」である「モルフェウス」の名を冠し、「モルヒネ(morphine)」と名付けます。
さて、このモルヒネの発見はいくつかの化学史上重大な意義を含んでいます。簡単に言いますと、このモルヒネは植物から「薬効成分」を分離した初めての事例でして、同時に「植物塩基」と称される「アルカロイド」(=その5参照)の単離に初めて成功した事例となります。ピンと来ないかも知れませんが、もし当時にノーベル賞があれば受賞確実、というレベルの話です。事実、この発表を契機として、当時の薬の主力だった各種植物の「有効成分」の分離が活発化し、マラリアの有効成分である「キニーネ」、御馴染みタバコの「ニコチン」、強心剤であるキツネノテブクロの「ジギタリス」、コカの葉から「コカイン」などその後重要な局面でたびたび使われることとなる成分が相次いで分離されるようになったことを考えれば、その影響は大きいと言えるでしょう。
モルヒネはその後も研究が続きまして、特に丁度この頃から動き始めた「有機化学」という分野の発展とともに構造などが色々と分かるようになります。ただ、こう言った部分はかなり「難物」だったようでして、構造解析は発見から100年以上経った1923年にガランドとロビンソンにより提出。そして、1927年にこの構造が確認されて確定します(これはこれでかなり段階があり、そしてもめています)。人工合成は1952年にアメリカのロチェスター大学のゲーツとチュッディらによってなされます。
以下に、モルヒネの構造を示しておきます。
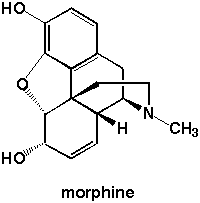
この人工合成もかなり難物でして、余り効率の良い方法はないみたいです(物すごく専門的な話ですが、Diels-Alder反応など色々と使うようです)。しかし、天然ではあっさり合成してくれるのが面白いものですが......とは言っても、自然と同じような合成手法を人工ではしませんが。
天然での合成経路は分かっていまして、原料はアミノ酸であるチロシンから出来ます(このチロシンは、天然物では他にもアドレナリンや他の幻覚剤、麻薬などを作りだす原料となっています)。
#興味ある学生さん向けに、ある程度の合成経路はこちらに示しておきます(一般的ではないです)。
モルヒネはケシの産地・栽培時期などで異りますが、概ね10%前後含まれています(日本製もこれくらい)。これを人に投与するとその効果は全くアヘンと一緒となります。つまり、中枢神経に抑制的に働きまして、鎮痛・鎮静作用を持ち、眠りを誘います。また、呼吸数が呼吸中枢への抑制作用により減少するのも特徴でして、一度に大量に用いた場合に死に至るのは、これが原因の窒息死となります(急性中毒になります)。
さて、こうしてアヘンよりモルヒネが分離されると、医療方面などでアヘンに変わってモルヒネが使用されるようになります。そして、1853年にアレキサンダー・ウッドにより皮下用注射器が開発されると、この使用は特に加速されます。この理由は「使用法」が関与しまして、アヘンならば経口投与(口から飲ませる)のが一般的(中国人は煙でしたが)ですが、量についての知識がちゃんとあればモルヒネを水溶液にして直接注射器で血中に流し込む、という手法がとれます。実際的にはこちらの方が確実性があり、しかも少量で効き(経口で取ると、身体に取り込まれるまでにロスが存在する→その4参照)、そして即効性があるという意味では重要な利点があります。
こうした意味において、皮下用注射器の発明は医療面でモルヒネとともにある種の「革命」をもたらすこととなるのですが.........しかし、同時に大きな弊害をもたらすこととなります。
モルヒネの注射は内服に比べると意識を失わせることなく鎮痛効果を迅速にもたらす、という側面がありました。これにより1861年のアメリカ南北戦争と1870年普仏戦争辺りから戦場を中心に広く用いられるようになります。そして、皮肉なことにこの皮下注射によって迅速に得られる鎮痛効果と多幸感により、兵士達の間でモルヒネ中毒が発生します。事実、南北戦争の多数の帰還兵がこの注射用モルヒネに耽溺となり、このことからモルヒネ中毒は「兵隊病」として広く知られることとなります。そして、アメリカでは南北戦争帰還兵向けにアヘンの通信販売をしていたことが知られており、その宣伝広告は今でも「史料」として残っています。
「夢の神」は兵士達を虜にした、ということになりますが..........
これから示されるように、皮下注射は医学的には大きな意義を持つと同時に、乱用へも大きな意味を持つようになります。そして、現在でもこの問題は継続していまして、他の薬物の使用に注射器を使用するケースがある(こちらは覚せい剤が一般的ですが)のはニュースなどでも御存じの通りかと思います。もっとも、注射による薬物使用は最近はエイズの感染問題に絡んで減少傾向、という話もありますが.........
さて、アヘンよりモルヒネが分離されてからもアヘンの中にどういう物が含まれているか、という研究は進み、やがていくつかの化合物がこれより分離されることとなります。その代表的なものはいずれもアルカロイドでして、アヘンより取れるので「アヘンアルカロイド」とも総称されます。この中でも精神に作用する成分はアヘンを英語で「opium」と言います(元はギリシア語)ので、ここからとれたことから「オピエート」とも呼ばれます。また、モルヒネの構造改変をして医療などで使用する研究も進むのですが、こちらは今回やると半端になりますし、すでにある程度長くなっていますので、次回に持ち越すこととしましょう。
そういうわけで、今回は以上ということで.........
終わり、と。
さて、今回の「からむこらむ」は如何だったでしょうか?
今回は前回主役だった「アヘン」についてと、その具体的な話をしてみましたが........ま、色々とアヘンから「始まった」という物が多いですので、ちょっと長くなりそうですけどね(^^;; ただ、これが色々な面での「基本」となりますので、その点は御理解のほどを。
ま、突っ込むとかなり面白いと同時に長くなったりするんですよね.........
さて、次回は取りあえずモルヒネの話まである程度出来ましたので、最後に書いた通りオピエートと、モルヒネの構造を変えた薬物などについて触れてみましょう。いずれも、有名な薬物になったりしますが.........結構奥深い部分でもあったりします。
#個人的には大好きな話なのですが(^^;;
そう言うことで、今回は以上です。
御感想、お待ちしていますm(__)m
次回をお楽しみに.......
(2001/05/08記述)
前回分 次回分
からむこらむトップへ