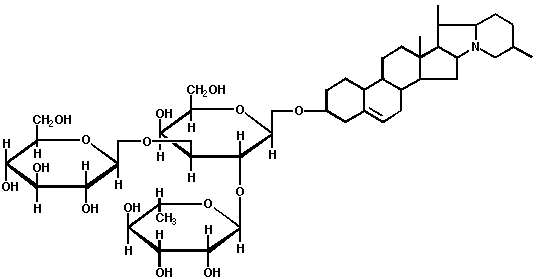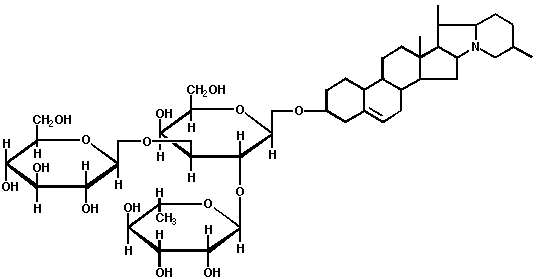からむこらむ
〜その94:王様と泥棒〜
まず最初に......
こんにちは。11月もいよいよ終わりとなりそうですが.......皆様如何お過ごしでしょうか?
管理人は.......誕生日ですね(笑) 四捨五入すれば30という領域なんですが........いやぁ、何にも感慨無いですね(笑)
さて、今回はちょっと色々とありまして「手抜き」と言うことで(^^;;
現在の主要な食料である物についての話、となりますが.........これに絡む毒、という事で。更に若干、ですけど。ま、ちょっとした息抜きみたいに読んで行って下さい。
それでは「王様と泥棒」の始まり始まり...........
昔の事。
ある国の皇帝は、ある作物を広めることに苦心していました。その皇帝は、その作物が皆にとって、必ず良いものであると分かっていたので、懸命に推奨しました。
しかし、そんな皇帝の努力にも関わらず、農民はその作物を嫌いました。「あれは悪魔の食いもんだ」「あれを食べたら病気になる」「貧乏人が食うもんだ」。そう言われていた作物を植えるのを、農民はひたすら避けてきました。皇帝も農民がそう思っているのを知っていたので、一生懸命説いて回りますが、農民はそれを聞きませんでした。
そんな様子が続いた皇帝は、ついに業を煮やします。
ある日、皇帝は農民に向けて次のような宣言をしました..............「命令に背くものの耳と鼻をそぎ落とす!」 驚いた農民の一部はその作物を植え始めました。でも、「悪魔の食いもん」と思っている人は多かったので、できる限り避けていました。
そんなしばらくの後。皇帝は退位し、その子が新しい皇帝となりました。でも、その新しい皇帝もこの作物を多いに推奨していました。農民はどうにか抵抗を試みましたが、これを見た皇帝はこの作物の栽培を奨めるため、騎兵の精鋭を村に送って、逆らおうとする農民を脅しました。
そんな事や、後には飢餓や手引書を作ったことも手伝って、後........この作物はこの国に広まりました..........
さて.......いきなりこんな話をしていますが..........
これ、中世ヨーロッパは当時はプロシアと呼ばれた、現在のドイツ東部でのお話です。皇帝はフリードリヒ1世。その子はフリードリヒ2世です。そして、この「悪魔の食いもん」と農民が恐れた作物は.........「じゃがいも」(馬鈴薯)でした。
そう、今日ではヨーロッパでは重要な食料となっている物だったのですが............広まったのは実は18世紀頃と言われています。
こういう話があった、って御存じでした?
さて、時はもうちょっと遡りまして大航海時代の頃。
コロンブスが新大陸を「発見」してから、この大陸へヨーロッパ各国は色々と触手を伸ばしていきますが.........この新大陸からヨーロッパが得たものには非常に大きなものがありました。例えば、当時治療法が無かったマラリアの特効薬であるキナノキ。またはタバコやコカと言ったもの。また、征服することで得た金銀財宝などたくさんありました。
そんな中の一つにじゃがいもがありました。
じゃがいもがヨーロッパにもたらされたのは、概ね16世紀半ば頃、と言われています。しかし、アンデス中南部産地原産........だいたいペルーのチチカカ湖周辺を原産とするこの食物は、ペルーやチリでは広く栽培されていたのですが、ヨーロッパでは最初観賞用として伝わった、と言われています。
このじゃがいも。実は、最初は食べ物としては非常に不評でして.........理由はいくつかあるようなのですが、「異教」であったマヤ教の食べ物、と言われたから、という話があります。もっとも、これは余り説得力はないのですが。何故ならば、同じく新大陸よりもたらされたタバコやサツマイモはヨーロッパの他各地に広まりましたから。また、別の理由としては不ぞろいの塊根の「形が良くない」という話もあるようです。また、フランスの『エンサイクロペディア』初版において、じゃがいもが「どんなに料理しても味が薄くでんぷんのようだ」という事で余り評判がよろしくなく、「食物の一つとして見なせない」という表記があるそうで、そう言ったことも理由の一つであったようですが。
しかし、『エンサイクロペディア』の第二版ではこの表記が変わった、と言われています。
実は、16世紀半ばの1565年。つまり、ヨーロッパにじゃがいもがもたらされた最初期の頃。新大陸よりスペインのアルマダ号なる船がペルーからの帰路に際して遭難。アイルランドに漂着し、積み荷を打ち上げた、という記録があります。これがアイルランドにもたらされたじゃがいもの最初の記録となっています。
さて、こうしてじゃがいもに出会ったアイルランドですが.........アイルランドは気候の問題から当時(今でも)重要な食料である麦などの作物が育ちにくいという特徴がありました。ですので、アイルランドの農家は大分食料に関しては難儀していたのですが.........このじゃがいもは、アイルランドの気候では栽培に適していることが判明し、アイルランドでは広まることとなります。
少なくとも、冒頭のプロシアの様な事はなかった様でして、19世紀にはすでに三度の食事に出てくるものとなっていました。この為、上記『エンサイクロペディア』の第二版において、アイルランドの事例を挙げて、「飢餓の際には最高の救荒植物である」と表記が変わったと言われています。確かに、じゃがいもに含まれるでんぷんは貴重な炭水化物源であり、また加熱してもでんぷんと結合したビタミンCは壊れず、他にもビタミン類やミネラル分がある、とあれば重要な食料源となりますが。
もっとも......このアイルランドのじゃがいも。1845年にイギリスで突然発生したカビによる植物病(べと病)が翌年アイルランドに及び、これによりじゃがいもが全滅した、という記録があります。「三度の食事に出てくる」この食べ物が全滅したことにより、栄養不足から飢餓と疫病が発生。100万以上とも言われる死者を出し、そして100万人以上がグレートブリテン島やアメリカへと逃れました。
この内、アメリカに逃れた一家に、後にジョン・フィッツジェラルド・ケネディ大統領を出すケネディ家がいた、と言うのがなんとも歴史の面白さを感じますが..........
ともかく、かくしてアイルランドを飢餓から救った食物は、それに依存しすぎたが故に逆に飢餓に陥った、という皮肉な歴史が有ったりします。
尚、日本では江戸時代。ジャガタラ(ジャカルタ)より来たオランダ船によりもたらされ、「ジャガタラいも」より「じゃがいも」としてその名称が広まりました。
漢字では「馬鈴薯」とも書きますが、江戸時代では「じゃがいも」として「清太夫芋」という字が当てられていたようです。「馬鈴薯」は秋の季語でもありますか。
余談ですが、よく混乱の元になりますが、じゃがいもは「茎」が発達したものです。ついでにナス科の植物でもあります。
さて、視点を大陸に移しましょう。
大陸ではアイルランドとは異なり、最初に表記したように、非常に農民から忌避されていました。その理由はいくつか述べましたが、もう少しありまして........一つは、じゃがいもは種子から発芽して育つ、という事もしますが(じゃがいもの実、と言うのもあります)、雌雄同体であり、更に塊根から発芽することで育つ.......つまり、「性的に不純な増殖」というキリスト教的には許しがたい事情があったこと(それにより、じゃがいもが裁判にかけられ、「火刑に処された」記録があるそうで)。そして、一つはある種のじゃがいもを食べると中毒症状を生じ、時として死に至る、という事があったのが原因となっていました。
ま、皆さんはおそらく大半の方は御存じとは思うのですが...........
じゃがいもを調理する際、芽の周囲を取る、という事をしていますよね? 芽とその周辺の緑色の部分は取るように言われると思うのですが.........料理をされる方でこれをしていない、という場合はかなり問題ですけど..........
何故か?
それは、発芽部分や緑色の部分に毒となる物質が含まれているから、となっています。その名を「ソラニン(solanine)」として知られています。
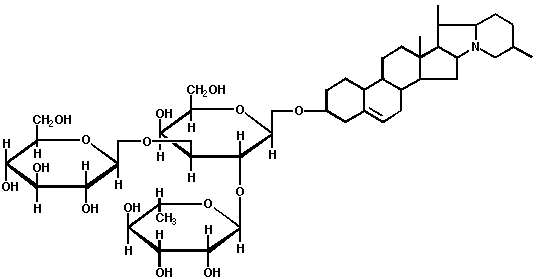
まぁ、大きい構造ですけど(^^;; え〜.......化学的には前回触れた「糖」が3種類左下でくっついています。で、右の方にはその70で触れたような「ステロイド骨格」を持った「ソラニジン(solanidine)」というものがくっついています。
#専門的には「ステロイドアルカロイド」と言われるタイプのものですが.........
最初、このソラニンは単一化合物と思われていたのですが、研究が進むといくつも出てきまして、今現在は「ソラニン類」として知られています。上記構造は「α-ソラニン」と呼ばれる物でして、糖の部分の構造や数によってβ、γが。そして、同じくα、β、γの「チャコニン(chaconine)という化合物が知られています。
尚、糖と別のものがくっついたこの化合物は、前回のラストの方で軽く触れている、「配糖体」と呼ばれる化合物の一種ともなっています。
#専門注:グリコアルカロイド(ステロイドアルカロイド配糖体)とも言われますが。
さて、このソラニン。通常じゃがいもでは0.004〜0.01%程度含有されています。が、貯蔵や栽培法が不適切な場合には緑色の部分が増えたり、発芽したりします。こうなるとその含有量は増加することが知られています。特に貯蔵法では「光に当てない」事が重要でして、光に当てることで発芽してしまいます。芽の部分には0.08〜0.1%含まれる事があるようです。付け加えるに、冷蔵するとじゃがいものでんぷんが変成しますので、暗所で風通しの良いところに保管することが重要となります。
ヒトに対する中毒量は0.2〜0.4gとなっていますので、じゃがいもの摂食量で変わりますが、ソラニン含有量が0.02〜0.04%を越えると危険領域となります。ただし、含有量が多いと味としてはエグ味が多くなるので、大体口にいれると分かると言われています。
作用としては抗コリンエステラーゼ作用となっていますので、その72、73。或いはその85で触れた神経の伝達の阻害を行います。食後数時間で症状が出て、腹痛、嘔吐、軽い幻覚を出しますが、時には意識不明となり、摂食量によっては死に至ります。
加熱などによって分解しませんので、調理の前に芽を取るか、皮の緑色の部分を除くことで中毒を避けることが出来ます。
尚、このソラニン。ある種の「抗菌成分」でして、本来は外部からの菌の侵入を防ぐための「防除物質」であることが知られています。
こう言った抗菌性物質は植物にはよく含まれまして、総称して「フィトアレキシン(phytoalexin)」と呼ばれています。ソラニンはこのフィトアレキシンの一つですが、他の植物のフィトアレキシン全部が人間に対しても毒、という訳ではなく、中には食べ物でよく含まれることがあります。例えば、ビールに不可欠のホップにはフムロン、ルプロンと呼ばれる抗菌成分があるのですが、これがビールの「苦味」の原因物質にもなっています。
余談ですが、遺伝子組み換え作物では、ここら辺の生産の強化、というのもあるようです。
ま、フィトアレキシンは別の機会に詳しく触れることとしましょう。
さて、考えると........じゃがいもに関してこのような知識があるわけではなかった当時のヨーロッパ。かなりこのソラニン中毒で悩まされたことがあったようで、「悪魔の食いもん」とか「貧乏人の食べ物」という、現在から見れば「不当な扱い」を受けていました。しかし、適切な栽培法に貯蔵法をすれば、非常に重要な食料源となるわけでして..........それに気付いたプロシアの皇帝は、最初に書いたような「過激な方法」を宣言してまでも普及に努めました。その結果、どうにかプロシアでは定着します。
しかし、隣国では事情が違っていました。
昔よりドイツとフランスというのはある種のライバル関係があるのですが...........プロシアでは定着したじゃがいもは、フランスではなかなか定着しませんでした。
さて、プロシアとフランスで行われた7年戦争に従軍して捕虜となった人物にフランスの薬剤師アントワーヌ・パルマンティエがいました。この人物、拘留中にじゃがいもを食べまして.........これが将来重要な食料となる、と気付きフランスに帰国後、時の国王ルイ15世にこの栽培の奨励を進言します。国王はこれに同意し、色々と策を練ります。しかし、フランスではじゃがいもはまだ「悪魔の食いもん」であり、「貧乏人が食べる」物でした。ですので、なかなか広まらず..........大分苦労したようでして、後にルイ16世の時代にはパルマンティエは国王にじゃがいもの花束を送ったと言われていますし、マリー・アントワネットはその髪をじゃがいもの花で飾ったとも言われていまして、懸命の「イメージ戦略」を行います。また、王はパリの貴族や、後に断頭台の露と消えるラヴォアジエ、雷の実験から避雷針を作りだし、後にアメリカ独立運動の指導者となる、ベンジャミン・フランクリンと言った著名人を「豪華なじゃがいも料理だけの晩餐会」(どういうのだか興味ありますが)に招待したりして、その普及に懸命になります。
さて、しかし........このような努力もプロシアの例に漏れず、なかなか農民には広まりません。これに悩んだ王とパルマンティエは対策として、あるアイデア.......少なくとも、プロシアの様な過激な方法に走らないアイデアを思いつき、実行に移します。
彼らが出したアイデアは、パリ郊外のレ・サブロンと言う荒れた土地にじゃがいも畑をこしらえる事から始まります。そして、そこに終日見張らせるために王宮の兵を一部隊配し、非常に厳重な警備をしきました。更にそこに札を立てて警告します........「この作物を盗んだものは厳罰に処す」と。
さて、こんなに物騒な配備がされる土地........人々は当然興味が引かれます。「あの土地には何があるのか?」「王があそこまで厳重に警備するところだから何か重要な物に違いない。」「少なくとも何か価値があるんだろう。」...........好奇心が徐々に膨らみます。その上、夜には警備に配された兵士達は引き上げてしまう、という事で........夜は隙だらけ。
かくして、普段は「悪魔の食いもん」として敬遠された作物は、何も知らない人達によって「重要なもの」に格上げされ、また、「王の大事な物を盗む」という好奇心(虚栄心? 功名?)も手伝って、「泥棒」となった住民達に盗まれていきました。もちろん、王とパルマンティエ達の目論み通り..........
かくして、このじゃがいもはフランスの住民達に広まっていった、と言われています。
最終的にはフランスではフランス革命以降の重大な食料難にぶち当たってから、じゃがいもの重要性が認識されて、そこから本格的に普及した様です。それは「大地のりんご」として重宝されるようになります。
まぁ、「王様と泥棒」。じゃがいもに関しては王様の頭脳プレイが勝利を収めた、と言うことになりますか............
さて、長くなりました。
今回は以上、と言うことにしましょう。
・2000/12/01補足
アイルランドでのじゃがいもの影響を示す資料がありましたので、他の補足も含めここに記しておきます。
アイルランドの人口は1730年には150万人であったのが、1845年には850万人と5.6倍の人口増加を示します。が、植物病(べと病)による影響でじゃがいもは不作となり、5年で100万人の人口減。1901年には440万人へと減少します。これにより、人口流出も加速化し、1840年代〜1920年代までにアイルランドで生まれた人口の43%が海外流出しています。
べと病はイギリスで発生しましたが、イギリスで栽培されていた小麦には影響を与えず、むしろ豊作と言われていました。が、じゃがいもはこれにやられてしまい、農地の2/3がじゃがいも畑だったアイルランドは深刻な事態になったようです。一応、小麦などもあったのですが、それらの農地はイギリスの不在地主の物で手が出せなかったと言われています。
#アイルランドはイギリスの産業革命以降、イギリスへの食料供給が求められ、小麦をイギリスへと輸出していました。これが飢餓の遠因となっています。
じゃがいもは南米で栽培されていたのにも関わらず、アメリカ大陸での伝播はメキシコ止まりでして、アイルランド系移民によって北米に伝わったと言われます。
結局長くなった(爆)
さて、今回の「からこら」は如何だったでしょうか?
え〜......今回は書く側としては非常に楽でしたけど........まぁ、内容は大分与太的に近いとは思います。一応、名前とかは有名な物質ですし、そこそこ有名な話だとは思うのですが..........どうでしたかね?
取りあえずは楽しんでいただけたら、と思います。
さて、次回相も変わらず決まっていませんが.........何にしますか(^^;;
適当に決めましょう。
さて、今回は以上です。
御感想、お待ちしていますm(__)m
次回をお楽しみに.............
(2000/11/28記述 12/01補足)
前回分 次回分
からむこらむトップへ